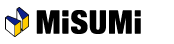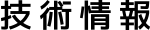メカニカル部品
- 日本のモノづくり現場が高付加価値化への傾向を強める関係で、振動問題の重要性が大きくなっています。質量を持つ装置の運動制御においては、高速化と精密化は相反する物理現象となるため高度な制御技術と免振技術を活用することが望まれます。以降では自動化の振動問題と対策について解説します。 1)振動と生産現場の問題 生産現場では、品質とコストと振動問題は直接的、間接的に深い関係があります。 例:タグ:
- 穴と棒の組付けには、2個の部品間の寸法関係で組付け作業も2種類に区分されます。 ここでは組付けに力を要す圧入について、用語解説をします。タグ:
- コンデンサやLSIリードフレームなどの電子部品を事例に、複数軸の同時自動挿入の勘所を解説します。 (1)複数軸の同時自動挿入の事例 ・コンデンサやLSIなどの電子部品を自動挿入する場合、挿入する部品は事前に専用のステック(整列挿入された保持キャリアケース)や整列トレイ内に整列されて供給されます。 ・挿入穴の幅寸法に対して、挿入する電子部品側の複数軸(LSIのリードなど)は規定公差以内の形状で成形されています。LSIリードフレームの場合、挿入穴に対して0°~10°程度の角度で広がった成形状態としています。 ・挿入穴に挿入させる前段階で複数軸の位置を成形して、挿入穴に挿入する時に基板を変形させたり振動を与えないことが求められます。 ・【図1】は、自動挿入装置のチャック部で複数軸を一定寸法に成形し、その状態で挿入する事例の解説図です。 ・挿入後に複数軸(LSIリード)の先端部の切断やかしめ(クリンチ処理)などの後処理を行う場合があります。タグ:
- 自動挿入機の設計においては、挿入する部品形状の特徴や挿入時に生じる力(挿入反力による変形など)を想像して、挿入部品の把持部設計をする必要があります。 (1)長い軸部品の自動挿入の事例 ・回路基板やプラスチック製ボード等への位置決め軸や回転軸などの自動挿入する場合(【図1】)、挿入軸は接着剤などは使用せずに挿入穴の弾性変形力で固定されます。 ・この様な挿入の場合、自動挿入で挿入ミスになると基板破壊や再生が難しいなどの厄介な作業ミスとなります。 ・挿入時の基板からの弾性変形は、予想外の複雑な反力を生じさせます。スティックスリップによる断続的な反発力や回転ねじれなど。この様な変動の影響を小さくする把持機構(【図3】参照)が勘所です。タグ:
- 挿入組付けのローコストオートメーションの自動化設計の勘所について事例解説をします。 (1)挿入組付け自動化設計の勘所 1.部品面取り寸法と位置決め必要精度の関係 挿入組付けする2個の部品の面取り寸法に対する自動機側の位置決めの必要精度は、【図1】の関係より出てきます。ローコストオートメーションの設計では、この関係式を満たす位置決め精度が必要条件です。タグ:
- 人による手作業を組立自動化(ローコストオートメーション化)するときに、機械設計者が忘れがちなこととして手作業の習熟性があります。この習熟性を自動化技術で対応しようとすると非常に複雑な機構と制御が必要となり、(1)生産タクトが長くなる、(2)自動機の故障停止が増える、(3)投資額が増大する、などのデメリットに繋がってきます。ここでは、挿入組付けの習熟性を可能な限り排除するための部品設計の勘所を解説します。 (1)挿入組付けしやすくする部品設計の勘所 自動機の設計者は、組立自動機の競争力を高めるために製品設計者に対し組立やすい部品設計を指導したり、その重要性を啓蒙するリーダーシップが求められます。下表がその勘所となります。タグ:
- 組立自動化の要素技術の3番目の代表事例として挿入組付け技術を解説します。 組立作業の自動化(LCA:ローコストオートメーション)は、複数の単純な要素作業の自動化を複合化させたものと言えます。技術講座では、「かしめ技術」、「ねじ締結技術」、「挿入組付け技術」を組立作業の自動化の代表的要素技術として解説しました。 (1)挿入組付け技術とは ・挿入組付け技術とは次のような作業を手作業または治具/装置で処理する手段です。タグ:
- ねじ締結の信頼性はねじ部品の品質(例えば、ボルトやナットの強度区分)とねじ締結作業の安定した処理で維持されます。ねじ締結に関するJIS規格の概要を解説します。 (1)ねじ部品の品質に関するJIS規格 JIS規格では次の内容が規定されています。
- ねじ締結作業に係る不良内容を分類し、ねじ締結装置のトラブル対策例を解説します。 (1)ねじ締結不良とその要因分類 ねじ締結不良は次のように分類できます。 このなかで、ねじ締結装置に関係ある不良内容として下記が挙げられます。 a)ねじ締結作業のミス
- ねじ締結ユニットはねじ締結自動装置の最重要機構です。ここでは代表的なねじ締結方式と自動装置の基本構造の事例を紹介します。 ねじ締結の方式 ねじ締結ユニットの事例 ねじ締結の方式 ねじ締結部の代表的な構成は次のようになります。 ねじ締結ユニットのねじ締め方式には次のような方式があります。締付け力のばらつきはa)>b)>c){高精度}の順で精度が向上できます。
- トラブル内容の比率が高いねじ部品の供給ミスの対策に役立つ生産技術を解説します。 ねじは、締結後の製品の特徴に応じて、a)ねじ頭の形状、b)ねじ部の形状、c)締め付け穴の形状、d)座金の有無、e)材料、表面処理の違い、その他、非常に多くの種類があります。したがって、ねじ部品供給装置にも多様な種類に応じた対応性が求められます。 (1)ねじ部品供給装置の構成 ねじ部品の供給装置の構成は次のようになります。 ねじ整列ユニット・・・ねじの貯蔵・整列・分離の処理を自動で行う装置。【写真1】参照
- 組立要素技術の代表には、“かしめ技術”のほかに“ねじ締結技術”があります。以下ではねじ締結作業の自動化に必要となる基礎的な技術を解説します。 (1)ねじ締結自動化の構成 ねじ締結作業を自動化するには、ねじ締結作業の前後を含めたシステム構成を明らかにする必要があります。ねじ締結自動化の構成は次のように作業分類できます。 (2)ねじ締結自動化における主なトラブル内容 ねじ締結自動化における主なトラブル内容を上記の3つの機能分割毎に整理すると次のようになります。したがって、下記の対処策を自動化に盛り込む必要があります。 1)ねじ部品供給の自動化に関する主なトラブル
- かしめ加工は高い生産性と併せて優れた締結信頼性を有していますが、一方で、再生作業が難しいため量産時点での加工条件の最適化が重要です。以下ではかしめ品質に影響を及ぼす代表的な制御因子を解説します。 (1)かしめ品質 かしめ品質には次の代表的項目が挙げられます。タグ:
- かしめの種類とその特徴を続けます。図の出典元は日刊工業新聞社発行の『組付け要素技術マニュアル』です。 1)つぶしかしめ 丸棒や丸パイプの外周一部をつぶして結合させる方法です。回転が可能な簡易的な留めピンなどに利用されます。タグ:
- かしめの種類とその特徴を解説します。図の出典元は日刊工業新聞社発行の組付け要素技術マニュアルです。 1)リベット結合 2枚の板状部品に貫通穴をあけ、その穴径より細いリベットを挿入しリベット両端をつぶして結合させる方法です。タグ:
- 一般的な製品は、複数の部品を機能的に組付けて組立製品となります。この組付け作業の段階で、低コストで安定品質が得られる(言い換えると作りやすい)製品設計と組立生産技術が、キーポイントとなります。さらに、環境問題の関係から、廃棄コストがかからない製品の特徴も求められてきます。これから、組立要素技術の代表の一つである“かしめ技術”について解説します。タグ:
- (1)スクリーン印刷 スクリーン印刷は、シンプルな印刷法です。ステンシル(シルクスクリーン)と呼ばれるインキを転写させる部分が貫通した版を用い、ゴム製へら(スキージと呼ばれる)で版上のインキを貫通穴から版の下に設置された印刷物に転写させる方式です。 (2)スクリーン印刷の特徴 長所:タグ:
- 型内組立用LCA(ローコストオートメーション)を構成するユニット 位置決めユニットの構造事例 型内組立用LCA(ローコストオートメーション)を構成するユニット 型内組立用LCA(ローコストオートメーション)は、次のユニットで構成されます。タグ:
- 化学打抜きに用いられるエッチング液(腐食液)は、金属材料や要求される加工速度などによって種々の組成と温度が用いられています。主な材料に対するエッチング液の組成とその条件の一例を【表1】に示しました。