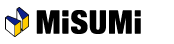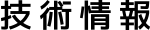射出成形:基礎知識
- プラスチック射出成形金型は、量産成形加工を続けていく途中で、部品の磨耗や破損などが必ず発生します。そのような場合には、部品交換や補修によるメンテナンスを行う必要があります。 メンテナンス事項には、一般的に下記のような内容があります。タグ:
- プラスチック成形品は、成形加工後に二次加工として塗装や色入れなどの色彩を付与することで付加価値を高める工程を採用する場合があります。文字やロゴマークの印刷、ウエルドラインやフローマークを目立たなくするための表面塗装、金属光沢を得るためのメタリック塗装などがあります。 塗装は塗料やインキを使用するのが一般的です。これらの組成は、ビヒクル、助剤及び顔料から構成されています。 ビヒクルは、樹脂と溶剤と添加剤を混合させたものです。 平板インキでは、樹脂としては石油樹脂、ロジン変性フェノール樹脂が主に使用されます。 グラビアインキでは、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂が主要な樹脂になります。 塗料では、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂が使用されています。 溶剤としては、平板インキでは高沸点石油系炭化水素溶剤が使用されています。 グラビアインキでは、イソプロピルアルコール、酢酸エチル等が採用されています。塗料ではキシレン、酢酸エチル、イソプロピルアルコールが利用されます。 助剤には、粘度調整剤、ゲル化剤、乾燥調整剤、可塑剤、滑剤、静電気防止剤、界面活性剤、消泡剤などがあります。タグ:
- プラスチック射出成形品の表面の硬さを試験するため方法として一般的に使用されているのは、ロックウエル硬さ試験です。 金型部品用の鋼材の試験方法としてロックウエル硬さ試験は多用されていますが、この場合の測定スケールはCスケールで、硬さは「50HRC」のように表記されます。 プラスチック成形品の硬さを測定する場合、Cスケールを使用した場合には鋼材と比較して大変柔らかいために正確な硬度を計測することができません。 そこで、プラスチック成形品の硬度を測定するためには「Rスケール」または「Lスケール」、「Mスケール」を使用します。 したがって計測した値は、「65HRR」、「80HRL」、「92HRM」のように表記されます。 各スケールは、以下の計測基準によって使い分けられます。タグ:
- 液晶ポリマー(LCP、Liqud Crystal Polymer)は、良好な耐熱性を有するスーパーエンジニアリングプラスチックとして電子部品、コネクターに採用されています。 液晶ポリマーは、成形品が薄肉であっても良好な流動性を示しているため、コネクター類などの薄肉小型精密成形品の射出成形も可能です。 表面実装方式(SMT)ではんだ付けされる部品では、今後、「鉛フリーはんだ」が環境対策として推奨される社会情勢があり、「鉛フリーはんだ」はSMT時の温度が260℃程度まで上昇させなければならないため、従来他の樹脂で使用されていた電子部品が液晶ポリマーに変更される例が増えてくると予想されています。 現在の日本での液晶ポリマーの需要量は年間9,000トン程度と推測されています(2006年)が、今後3年ぐらいの間には需要量は30%程度増加するという予測もあります。 液晶ポリマーは優良な耐熱性、薄肉流動性を有する反面、以下のような成形加工上の難点があります。 (1)ウエルド強度 液晶ポリマーは流動性は良好であってもウエルド部の密着強度が低いという欠点があります。金型設計上ではこのポイントをいかに克服する構造を採用するかが重要な部分になります。タグ:
- 熱可塑性エラストマー(TPE、Thermo Plastic Elastmer)は、射出成形が可能なゴム状の成形材料で、各種の用途で実用化されています。 熱可塑性エラストマーには、いくつかの種類があって、特性ごとに応用分野が異なってきます。 以下に主な種類と特性を紹介します。
- プラスチック原材料の中でも最近、射出成形材料として使用される頻度が多くなっている材料としては、次のようなものがあります。当然に、これらの材料を使用する金型の新規生産も、増加していると考えて良いと思います。 (1)ポリカーボネイト(PC) 国内生産量41万トンと大量に生産されており、液晶テレビモニター、DVDプレーヤー、携帯電話筐体、導光板、TFT関連、電池パック、プリンター部品、自動車用照明部品などに採用されている。 透明度が良好で、高強度、高耐熱性であるが、成形加工性は悪く、流動性が低いので、高い圧力で金型内に充填させなければならない。金型温度も高く設定する機構が必要になる。 最近では、バルブゲートを使用することで、これらの問題を解決する技術も登場している。 (2)ポリフェニレンサルファイド(PPS) 国内生産量2万トンもの生産量になり、表面実装対応耐熱電子部品、光ピックアップ、自動車部品等へ使用されている。ガラス繊維を混ぜて使用する例も多い。流動性は良好である反面、僅かの金型の隙間でも流入しやすいのでバリが発生しやすい。金型温度は150℃程度にまで上げなければならない。 需要に対して生産が追いつかない状況が続いている。タグ:
- プラスチック射出成形機の型締め力が5〜20トンクラスの小型成形機が、国内外で好調に導入されるようになってきています。 これらの小型成形機を使用して、微細で精密な樹脂成形品を生産する需要が急速に伸びているためです。 また、さらに1ランク小さな成形品の成形加工は、「マイクロ成形」と呼ばれています。 マイクロ成形は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems、マイクロ電子機械システム)やマイクロ化学等の分野で使用される微細プラスチック部品を生産するために使用されます。 このような小型成形機やマイクロ成形機で使用される金型は、従来使用されている金型よりも一回り小さく、精密に工作されている必要があります。 具体的には、下記のような部分についての要素技術が重要になってきます。タグ:
- プラスチック成形材料は、一般にペレット状態に加工されて、紙袋などに入れられて原材料メーカーから搬入されてきます。 ペレットには、大気中の水分が吸湿されていますので、水分が多く含まれたままで射出成形加工してしまいますと、樹脂の種類によっては加水分解を発生したり、物性が低下したりする場合があります。また、銀条(シルバーストリーク)が成形品の表面に発生したり、ガスによるショートショットや焼けが発生しやすくなる場合もあります。 そこで、成形材料の多くは、ホッパードライヤーへ投入する前に、箱形乾燥炉で予備乾燥させることが必要になります。 予備乾燥は、適切な乾燥温度と乾燥時間を守ることが推奨されます。適正な温度以下でいくら長時間乾燥させても、水分は思うように排除できない場合があるからです。予備乾燥が終わった材料は、できるだけ早く使いきるようにします。余ってしまった材料を後日使用する場合には、再度の予備乾燥を行いましょう。 【表1】には、特殊なプラスチックの予備乾燥条件を示しています。 【表1】プラスチック成形材料の予備乾燥湿度
- プラスチック成形品を、他のプラスチック部品と接合して使用する事例もたくさんあります。プラスチック部品どうしを接合する手段には、以下のような方法があります。 (1)接着 接着剤を使用して接合する方法です。プラモデルの接合と原理は同じです。ホットメルト剤を使用して、より強固に接着する方法もあります。 (2)超音波溶着 超音波を接合面に発振させて、摩擦熱によって溶着させる方法です。短時間で比較的精密に接合ができます。超音波溶着機が必要になり、成形品の接合部分によって専用のホーンを製作する必要があります。 (3)熱風溶接 熱風を吹きかけて軟化させた部分を接合させる方法です。単純な方法ですので、精密な溶着には向いていません。 (4)スピン溶接 円筒形状の成形品を回転させながら接合させる方法です。接合面に発生する摩擦熱を利用します。 (5)摩擦溶接 接合面どうしを摩擦させて、発生する熱で溶着させる方法です。タグ:
- 金型から生み出されたプラスチック成形品は、その表面に着色したり、文字を印刷したりして、機能を向上させる二次加工がなされる場合があります。 プラスチック成形品に施される表面処理には、以下のような種類があります。 (1)塗装 有機系の塗料(いわゆるペンキのような塗料)等を、刷毛(はけ)で塗布したり、スプレー塗装する方法です。 用途によってマスキングを施したり、塗装の雰囲気を特別にしたりする工夫がなされます。 静電塗装や焼き付け塗装などの特殊な方法もあります。 (2)印刷 シルクスクリーン印刷、タンポ印刷、浸透印刷などがあります。文字や図柄を印刷する方法です。 印刷する場所が曲面であると結構印刷が困難になりますので、成形品の設計の際には、印刷したい場所は平面になるような工夫を盛り込むと良いでしょう。 (3)フィルム転写 薄い樹脂製フィルムに、あらかじめ印刷されている文字や絵柄を転写させる方法です。 金型の内部で転写させるインモールド転写法も開発されています。タグ:
- ポリサルホンは、耐熱水性が良好な透明樹脂です。酸やアルカリにも強く、機械的特性も安定しています。 食品や医療用の安全性が良好なので、この分野では採用例が増えています。 ただし、有機溶剤に対しては弱いので注意が必要です。 ガラス繊維強化も行われています。 主な用途は次の通りです。タグ:
- 液晶ポリマー(Liquid Crystal Polymer、LCP)は、耐熱性の良好な結晶性樹脂です。 ガラス繊維を30〜40%程度強化することで、荷重たわみ温度は270〜310℃程度まで上昇させることができるので、表面実装用対応用の精密電子部品に採用されています。 電気特性や振動吸収性能も良好です。自己消火性もあります。 溶融粘度は低く、流動性が良好なので、射出成形はしやすい樹脂です。その割には、冷却固化速度が速いので、ばりは発生しにくい長所を持っています。 反面、ウエルド部の接合強度が低いために成形品の形状によっては、工夫が必要になる場合があります。 また、流動方向と流動直角方向の成形収縮率に差がありあますので、金型設計にはノウハウの活用が必要になります。 金型の表面温度は、100〜150℃程度まで上げなければなりませんので、油による温度調節や電気ヒーターによる温度調節が必要になります。 ポリフェニレンサルファイドと並んで、電子部品用のスーパーエンプラとして各方面電子関連分野で採用が進んでいます。タグ:
- ポリプロピレンは、軽量で耐熱性の良好な結晶性樹脂です。半透明なグレードもあります。 ポリプロピレンは、特にヒンジ部の繰り返し疲労特性が良好で、他の樹脂に比べて優れた特徴を持っています。また、食品関係に使用しても安全性が良好なので、様々な容器類に利用されています。 ガラス繊維による強化も可能で、自動車部品にはこのタイプが多用されています。 溶融時の粘度が低いので、金型を製作する場合には、入れ子の分割面のクリアランスが大きすぎると、ばりが出やすいので注意が必要です。 また結晶性ですから、金型の温度管理状態によって成形収縮率も変動しやすいので、留意をします。 代表的な使用例としては、次のようなものがあります。タグ:
- ポリスチレンは、耐薬品性が良好な透明樹脂です。射出成形加工ができる樹脂として古くから多用されてきました。 家電の普及に従って、様々な分野で使用されている身近な存在でもあります。 粒状のゴム成分を分散させることによって、耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)が開発されたことで、大型家電の筐体に採用されるようになってきています。 また、食品容器関連ではいろいろなジャンルで実用化されています。透明なので、容器には適しています。 主な用途は、以下のようなものがあります。タグ:
- 最近商品化された透明なプラスチックです。非晶性樹脂であって、軽量、耐薬品性も良好です。 光学的特性では複屈折率が低く、アクリル樹脂と同水準の性能を有しています。また、吸水率も低く、耐熱性があるのでスチーム滅菌もできますから、薬品関連にも使いやすい特徴を持っています。 射出成形性にも優れており、光学分野や医療分野で実用化が進んでいます。 金型の転写性能も優秀です。 これからの新しい透明樹脂の一つとして注目されています。 これまでに開発された代表的な実用用途には、次のようなものがあります。タグ:
- ABS樹脂は、非晶性樹脂であって、アクリロニトリルとブタジエンとスチレンからなる共重合体です。 汎用プラスチックの中では、安定した強さと美しい光沢が得られ、家電製品を中心に幅広く使用されています。 成形品の表面にめっきを施したり、スパッタリングも可能です。 ただし、屋外での耐候性が優秀ではない点が指摘される場合もあります。 ポリカーボネイトやPBT、ポリアミド等と、ポリマーアロイを構成させて使用する例も増えています。 主要な用途には、以下のような事例があります。タグ:
- アクリル樹脂(メタクリル酸メチルエステル、PMMA)は、透明な非晶性の樹脂で、レンズや照明関係に古くから利用されています。 最近では、素材に他の化学成分を加えて改質が行われ、性能が向上されているグレードも各種開発されています。 アクリル樹脂の最大の特長は、光線透過率が優れている点です。樹脂の中では最も優れた性能を有しています。 また、表面硬度も高いので傷に対して抵抗力があります。コーティングにより硬度はさらに改良ができます。 耐候性も比較的良好な部類に属します。 主要な用途には、以下のような事例があります。タグ:
- ポリエチレンテレフタレート(PET)は、ペットボトルに使用されている透明な飽和ポリエステル樹脂です。 耐薬品性、耐熱性が良好であるので、食品容器類を中心に利用されています。 また疲労強度も良好で、電気特性も優れています。 ガスバリア性は極めて優秀です。 しかし、フェノールやクレゾールには侵食されます。 射出成形やブロー成形で使用されています。 主要な用途は、次の通りです。タグ:
- PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)は、荷重たわみ温度が260℃近辺まで耐えられるスーパーエンプラです。 架橋型、半架橋型、直鎖型の種類があります。 はんだの融点よりも荷重たわみ温度が高いので、リフローはんだ用の表面実装対応の電子部品に多用されています。 流動性が良いために、射出成形ではバリが発生しやすい特徴があります。 金型温度は130〜150℃まで上げる必要がありますので、金型は油での温度調節やカートリッジヒータによる保温が必要です。 材料の価格は高価でしたが、量産効果によって最近ではリーズナブルな価格帯へ落ち着いてきています。 主要な用途は、次の通りです。タグ:
- ポリカーボネイトは、透明で、強度が高い耐熱樹脂として、広い分野で応用が図られています。 最近では、ABS樹脂等とアロイにしたタイプも、工業用として多用されています。 非晶性であって、光線透過率も良好でありレンズやカバー類には好適な樹脂の一つです。強度的にも優秀で、特に耐衝撃性はプラスチックの中でも上位に位置しています。 ただし、有機溶剤には侵されるので、グリス類や溶剤が塗布されるような場合には注意が必要です。 射出成形では、流動性が悪いので、充填圧力は高めに設定しなければなりません。また金型温度も80℃程度まで上げる必要があります。 具体的な使用例としては、下記のような用途があります。タグ: