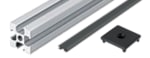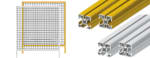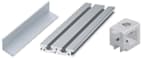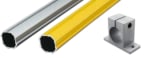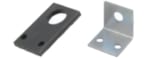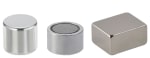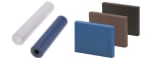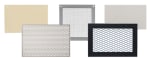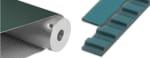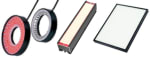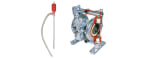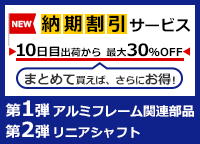(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
カテゴリ・メーカーから探す
メカニカル部品系
筐体・調整締結・素材
- フレーム・サポート部品・支柱
- キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品
-
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
-
六角穴付きボルト
-
六角ボルト
-
小ねじ
-
止めねじ
-
座金組込みねじ
-
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
-
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
-
でんでんボルト
-
アイボルト
-
樹脂ねじ・セラミックねじ
-
全ねじ・スタッドボルト
-
いたずら防止ねじ
-
配管Uボルト
-
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
-
マイクロねじ・微細ねじ
-
脱落防止ねじ
-
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
-
ドリルねじ
-
四角ボルト・丸ボルト
-
貫通穴付ボルト
-
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
-
座金(ねじ用ワッシャ)
-
ナット
-
アンカーボルト
-
リベット・鋲
-
インサート
-
建材用スクリュー
-
ねじ用工具類
-
ワッシャ・カラー
-
シム
-
スナップピン・割りピン
-
マシンキー
-
止め輪・リング
-
スクリュープラグ
-
アジャスタ
-
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
-
-
ばね・アブソーバ・調整締結・ピン・小物部品
-
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
-
対策・メンテナンス関連
空圧・油圧・配管・温調部品
回転伝達・コンベヤ・モータ・ロボット
直動・センサ・位置決め・ステージ
特注部品・図面加工部品
電気系
金型系
消耗品・補修用品・備品系
切削加工用品
-
切削工具
切削工具
-
エンドミル
-
フライスチップ・ホルダー
-
ヘッド交換式工具
-
自由指定直刃エンドミル
-
専用カッター
-
旋削チップ
-
旋削ホルダ
-
完成バイト・ロウ付けバイト
-
ローレット
-
ドリル
-
ドリル関連部品・用品
-
タップ
-
タップ関連部品・用品
-
ダイス
-
ダイス関連部品・用品
-
ねじ山修正・除去工具
-
タップ・ダイスセット
-
ねじ切りカッター
-
リーマ
-
面取りカッター
-
面取りカッター関連部品・用品
-
切削工具関連備品
-
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
-
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
-
磁気ボール盤カッター
-
ボーリングシステム
-
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
-
アングルヘッド
-
コレット
-
スリーブ・ソケット(ツーリング)
-
アーバ
-
ツーリング関連部品・用品
-
加工物基準位置測定器
-
芯出しバー
-
刃先位置測定器
-
ツールプリセッター
-
テストバー
-
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
-
クーラントライナー・クーラントシステム
-
エアージェット・エアークーラー
-
クーラント関連部品・用品
-
円テーブル・ロータリーテーブル
-
- 工作機工具・治具
生産加工用品
-
測定工具・計測機器
測定工具・計測機器
-
ノギス
-
pH計・導電率計
-
ノギス関連アクセサリ
-
マイクロメーター
-
検知管
-
ダイヤルゲージ
-
ダイヤルゲージ関連部品・用品
-
ピンゲージ
-
ピンゲージ関連部品・用品
-
ハイトゲージ
-
流量計
-
ハイトゲージ関連部品・用品
-
リングゲージ
-
デプスゲージ
-
シックネスゲージ・すきまゲージ
-
内径測定器
-
ゲージ
-
スコヤ
-
定規
-
コンベックス
-
巻尺
-
はかり
-
角度計
-
光学機器
-
水平器
-
レーザー測定器
-
マグネット関連
-
定盤
-
数取器・カウンタ
-
ガス測定器・検知器
-
ケガキ用品
-
ストップウォッチ・タイマー
-
テンションゲージ
-
環境測定器
-
温度計・湿度計
-
圧力計
-
顕微鏡
-
天秤・天秤関連品
-
分銅
-
硬度計
-
振動計・回転計
-
水質・水分測定器
-
粘度計
-
膜厚計・探知器
-
偏心測定器
-
表面粗さ測定器
-
音検出器
-
測定データ機器
-
アースメータ(接地抵抗計)
-
テスタ・マルチメータ
-
オシロスコープ
-
クランプメータ
-
検相器・検電器・導通チェッカ
-
絶縁抵抗計
-
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
-
安全試験器
-
回路素子測定器
-
信号源・ファンクションジェネレータ
-
電源装置
-
高周波測定器(RF測定器)
-
計測機器関連品
-
電圧計・電流計
-
電力計
-
その他電気計測器
-
- 放電加工用品
- 研削研磨・切断用品
-
手作業工具
手作業工具
-
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
-
六角棒レンチ
-
モンキーレンチ
-
トルクスレンチ
-
ソケットレンチ
-
トルクレンチ
-
トルクレンチ関連部品・用品
-
トルク測定器
-
ドライバー
-
ドライバー関連部品・用品
-
トルクドライバー
-
トルクドライバー関連部品・用品
-
プライヤー
-
プライヤー関連部品
-
ニッパー
-
ニッパー関連部品
-
ペンチ
-
ペンチ関連部品
-
ハンマー
-
工具セット・ツールセット
-
工具セット・ツールセット関連部品・用品
-
カッターナイフ
-
タガネ
-
ドライバービット
-
ドライバービット関連用品
-
プーラ
-
刻印・ポンチ
-
車輌整備用工具
-
水道・空調配管用工具
-
切断用工具
-
絶縁工具
-
板金用工具
-
防爆工具
-
かしめ工具
-
電設工具
-
バール・テコ
-
ソケットビット
-
ソケットアダプター
-
ピンセット
-
-
電動工具・空圧工具
- 小型加工機・卓上加工機
- 溶接用品
- はんだ・静電気対策用品
MRO・工場用副資材
メーカーから探す
特集から探す
- 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
- 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら
FA小ネタの部屋
FAにまつわる雑学を博士がわかりやすく解説!設計の合間の息抜きにどうぞ
No.13 ~安全第一編~
-
Q
製造業界では、誰しも一度は聞いたことがある言葉「安全第一」。
これは、工場や建設現場などの職場において安全を何よりも重要に考えるという意味のスローガンです。
さて、実は「安全第一」のスローガンには続きがあります。それは何でしょうか。
1. 生産第二、品質第三
2. 品質第二、生産第三
3. 顧客第二、品質第三 -
A
正解は、2.品質第二、生産第三
「安全第一、品質第二、生産第三」は元々アメリカで生まれたスローガンだったが、当初は「生産第一、品質第二、安全第三」というスローガンでした。
しかし、生産を重視するあまり労働災害が多発していたことから、現在のスローガンに切り替えられたそうです。
また、日本では1912年に現在のスローガンが入ってきました。最初は「安全第一」ではなく、「安全専一」と呼ばれていたそうです。
No.12 ~回転寿司編~
-
Q
日本を代表するソウルフード、お寿司!
お正月に召し上がった方も多いのではないでしょうか。
さて、お子様にも人気の「回転寿司」は、実は工場の中の「ある物」をヒントに開発されたそうです。
1. ベルトコンベヤ
2. 電動機(モーター)
3. 旋盤 -
A
正解は、1.ベルトコンベヤ
回転寿司のレーンを最初に生み出したのは、元禄産業株式会社の創設者である白石義明氏でした。
彼は、立ち食い寿司店を経営するにあたりお客さまの多さに対して寿司職人が少なく、お店がうまく回らない状況に陥っていました。
その時にたまたま工場見学したビール工場の製造に使われているベルトコンベヤからヒントを得て開発した「旋回式食事台」が、
当時は高級食であった「寿司」を手軽な大衆食にし、今日の回転寿司の基礎を築きあげたのが始まりだったそうです。
No.11 ~産業の〇〇編~
-
Q
日本が高度成長期にあった時代、鉄鋼は「産業のコメ」と呼ばれていました。
それは経済発展の中核を担うモノを指し、近年では半導体がそう呼ばれるなど、時代とともに変わっていきます。
それでは、現在、産業の塩と呼ばれているものは何でしょう?
1. 電気
2. ねじ
3. 製造業界で働く皆さんが流す汗の結晶 -
A
正解は、2. ねじ。
料理でいう「塩」のように、目立たないがどんなものにも使われていて、なくてはならないもの、という意味が込められているようです。
時代によって移り変わるとお伝えしましたが、最近では、「塩」といえば水晶デバイス、という考え方も出てきています。電子機器になくてはならないものだからですね。
ほかにも、「ハイテク産業のビタミン」はレアメタルと言われています。その重要性をたとえた表現を探してみると、興味深い発見がありそうです。
No.10 ~富岡製糸場編~
-
Q
明治5年10月4日は、富岡製糸場が操業を開始した日です。
オートメーション化のモデル工場となったことでも有名ですね。
「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録されますが、製糸場以外に「絹産業遺産群」も指定されています。
それはどんな背景があったからでしょう?
ヒント:黒船来航により、急速な近代化が必要だったが… -
A
江戸末期、黒船来航により突如として欧米の技術力を目の当たりにした日本は、近代化を急ぎます。
その上で重要な役割を果たすのが、重工業による産業化です。
しかし、そのためには初期の設備投資等にあてる膨大な資金が必要です。
ただ、当時の日本には、その資金がなかった…
そこで、絹産業(軽工業)に目を付けました。
もともと広く行われていた生糸の生産にフランスの技術を導入し、
高品質の生糸を生産して輸出し、大成功をおさめました。
そこで得たお金を使い、日本は本格的な産業革命を推し進めることができたのです。
その歴史背景を含めた遺産のため、富岡製糸場だけではなく、絹産業遺産群として世界遺産登録がなされました。
参考:特定非営利活動法人 世界遺産アカデミー
No.9 ~電話編~
-
Q
9/11は公衆電話の日です。
電話を発明したベルは、家族の職業に大きく影響を受け、この世紀の発明を成し遂げたといわれています。
どのような職業だったでしょう。
1. 父と母が、ピアノ奏者だった
2. 祖父と父が、声の研究者だった
3. 年の離れた兄が、解剖学者だった -
A
正解は、2.祖父と父が、声の研究者だった。
ベルの祖父は弁論術と発声法の大家で、父は読唇術の創始者だったといわれています。
母はピアノ奏者で、ベルにピアノと芸術を教えていましたが、父は奏者ではなかったので、1はひっかけとなります。
母は聴覚に障がいを持っており、その症状が進行した際に、ベルは家族のサポートのもと、手話を習得し、音響学の学習を開始しました。
その後、ベルは音の研究に熱を入れ、のちに世界初の電話を発明しました。偉大な発明には、このような背景があったのですね。
No.8 ~エアコン編~
-
Q
夏の必需品、エアコン。1850年、エアコンの原型となる製氷機がアメリカ人医師によって製作されました。
一般にどのように公開されたでしょう。
1. 氷で室温を下げた病室を開放した
2. パーティーで冷たいワインをふるまった
3. キンキンに冷やしたそうめんを提供した -
A
正解は、2.パーティーで冷たいワインをふるまった。
1850年7月、アメリカのフロリダは例年通り、暑い夏を迎えました。
フランス領事館が主催したパーティで、医師のジョン・ゴリーは、自作の製氷機で作った氷でワインを冷やし、お披露目したそうです。
その日はパリ祭。フランス革命ではフランスは市民たちに望むものを提供したということに結びつけ、
「本日は領事館も、みなさんの欲しいものを提供します。…それは、冷えたワインです!」と発表してふるまったとか。
その時代、氷は大変貴重だったため、夏に冷たいワインを飲む機会は滅多になかったとのこと。
新しい技術の公開の仕方も、気が利いていますね。
No.7 ~扇風機編~
-
Q
暑い夏、扇風機が活躍する季節がやってきました。
明治時代の中期には扇風機の初期型が発売されましたが、当時あるものが付いていました。それは何でしょう。
1. 電球
2. ラジオ
3. 簡易掃除機 -
A
正解は、1.電球。
スイッチを入れると、扇風機が回るとともに、電球がともりました。
現在のように電動機を使った扇風機が日本に登場したのは、1890年代の終わりごろ。
当時は家庭用電気製品といえば、白熱電球か扇風機という時代だったため、どちらも備えた扇風機は世間の注目の的になったようです。
なぜ電球がつけられたかは明らかになっていませんが、不安定な電流を安定させるための抵抗としてつけたという説が有力です。
No.6 ~ばね編~
-
Q
「ばね」は英語で「spring」。「春」も同じ単語を使います。
では、なぜ同じ単語を使うようになったのでしょう。語源を考えてみましょう。
1. 春になり、気分が高揚した子供がばねのように跳びはね始めたため
2. ばね→飛び出す→泉が湧き出す→春、という風に連想されていった
3. 古代ギリシャでばねを使った弓機の世界大会が開かれるのが、毎年春だった -
A
正解は、2.ばね→飛び出す→泉が湧き出す→春、という風に連想されていった。
寒い冬が終わり、待ちに待った暖かい春が来る。
その春の語源が「ばね」にあったと知ると、さらに味わい深い季節になるかもしれませんね。
No.5 ~ゴム編~
-
Q
広く使われる「ゴム」。
実は発見から実用までの歴史は長く、弾性や強度の欠点を克服する必要がありました。
ある時、アメリカの研究者がふとした偶然から突破口を発見します。
何をした時でしょう。
1. 牛脂と勘違いし、フライパンに乗せ料理した時
2. 実験中に居眠りし、ストーブの前に放置した時
3. 研究を諦めようと素材をかき集め、火にくべた時 -
A
正解は、2. 実験中に居眠りし、ストーブの前に放置した時。
アメリカ人発明家のチャールズ・グッドイヤーは、猛暑でも溶けない「ゴム」の研究をしていました。
10年近くあらゆる手を尽くしましたが、良い方法が見つからず途方に暮れる日々が続きました。そんなある日、ゴムをストーブの前にうっかり放置してしまいました。
ゴム表面にはわずかな保護膜ができ、それ以上は溶けていないことを発見しました。これが「加硫」という処理法につながります。
きっかけは偶然のできごとですが、成果を追い求めて研究を続けた根気強さと、些細な変化を見極める磨き抜かれた観察眼が突破口になった逸話として知られています。
No.4 ~2月特別編~
-
Q
今日は節分。みなさん、豆はまきましたか?
この中で、豆まきをしなくていいと言われている人がいます。一体だれでしょう?
1. 京都より北に住む人
2. 名字がワタナベの人
3. 正月に餅を10個以上食べた人 -
A
正解は、2.名字がワタナベの人。
時は遡り、平安時代。数々の悪事を働く鬼の大親分、酒呑童子を、武将・渡辺綱の一行がみごと退治したという逸話から、「ワタナベ」姓の者は豆まきをしなくてもよいという風習が広がったのだといいます。この鬼退治を題材にした浮世絵は多く残っており、鬼たちの描き方から当時の価値観がみてとれます。今年の節分は、知ってるようで知らない、鬼について調べてみても面白いかもしれませんね。
-
Q
明治の産業革命の象徴として、世界遺産を保有する街、北九州市。
おみやげとして、鋳物とそっくりの工程で作られているチョコレートがあります。それは何でしょう?
1. 実際にかみ合う歯車
2. ねじが回せるボルト&ナット
3. 組み立てできるアルミフレーム -
A
正解は、2のねじが回せるボルト&ナット。
観光客の増加に伴い、北九州オリジナルのおみやげを作ろうと、2016年に北九州の洋菓子店で開発されました。
作り方は以下の通り。
・3Dプリンタで最終製品と同じ形のモデルを作る
・食品用シリコンでねじ用とナット用の型を起こす
・型にチョコレートを流し込み、手作業で型からはずす
この工程が「鋳物とそっくり」なのです。
何度も試作を重ね、ねじの回しやすさを追求したのだとか。
北九州市へ訪問した際には、おみやげで買ってみては?
> ねじみたいに回せる!北九州土産の新定番「ネジチョコ」とは?
No.3 ~静電気編~
-
Q
冬はパチっと静電気の季節。
その性質は身近なものにも使われています。
この中で静電気が使われているものは何でしょう?
1. サランラップ
2. コピー機
3. お正月の風物詩、凧揚げの凧 -
A
答えは、1のサランラップと、2のコピー機です。
サランラップは、ラップを引き出す時に静電気を発生させ、静電気の力で物と密着させます。(静電気の他にもファンデルワールス力、減圧吸着の力も使われています)
コピー機は、静電気のない部分にトナーが吸着する仕組みを利用し、印字する/しない部分を分け、プリントしています。
パチっと痛いだけと思いがちですが、身近なところで使われている力なのですね。
No.2 ~ボルト編~
-
Q
きれいに並べると気持ちがいい六角レンチ。
なぜ六角か、ご存じですか?
説1. 実はDNAの塩基の形状に由来する
説2. 鎌倉時代に勢力を誇った武家の六角家が広めたため
説3. 亀の甲羅の六角形でボルトの原型を作ったのが始まり -
A
前回のねじに引き続き、実は明確な答えはありません。
四角、八角ではなぜNGなのか?を考えてみると、答えが見つかるかもしれません。
四角だと、角が直角のため工具がスムーズにかけにくく、またそのために角とレンチが接触し、欠けやすくなることが考えられます。
八角だと、工具とボルトの接触面積が小さくなり、ボルトにかかる力が少なくなります。
それらを踏まえた上で、もっともバランスが取れているのが六角なので、六角が普及したのかもしれませんね。
No.1 ~ねじ編~
-
Q
ねじは基本的に右回り。それは右利きが多いから?
なぜ右利きの人が多いか、知っていますか?
A. 地球の自転が右回りだから
B. 左にある心臓を右手で守るため
C. 最初に火起こしの道具を作った人がたまたま右利きだったから -
A
実は明確な答えはありません。
ただ、通説ですが、進化の過程で人類が集団で暮らすようになり、「言葉」がよく使われるようになったことが原因と言われています。
それにより、言葉を話すときに使う「言語野」のある左脳が発達しました。
左脳は右手と右足に直結しているため、右利きの人が多くなったという説があります。
では、左利きには一体どんなカラクリがあるのか?それはまた今度にしましょう。脳の世界は奥深いですね。