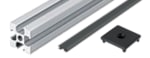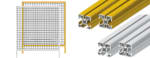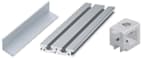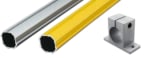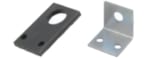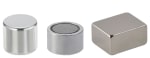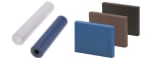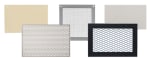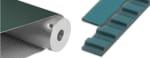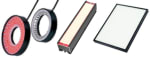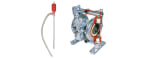(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
カテゴリ・メーカーから探す
メカニカル部品系
筐体・調整締結・素材
- フレーム・サポート部品・支柱
- キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品
-
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
-
六角穴付きボルト
-
脱落防止ねじ
-
貫通穴付ボルト
-
六角ボルト
-
小ねじ
-
止めねじ
-
座金組込みねじ
-
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
-
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
-
でんでんボルト
-
アイボルト
-
樹脂ねじ・セラミックねじ
-
全ねじ・スタッドボルト
-
いたずら防止ねじ
-
配管Uボルト
-
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
-
マイクロねじ・微細ねじ
-
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
-
ドリルねじ
-
四角ボルト・丸ボルト
-
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
-
座金(ねじ用ワッシャ)
-
ナット
-
アンカーボルト
-
リベット・鋲
-
インサート
-
建材用スクリュー
-
ねじ用工具類
-
ワッシャ・カラー
-
シム
-
スナップピン・割りピン
-
マシンキー
-
止め輪・リング
-
スクリュープラグ
-
アジャスタ
-
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
-
-
ばね・アブソーバ・調整締結・ピン・小物部品
-
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
-
対策・メンテナンス関連
空圧・油圧・配管・温調部品
回転伝達・コンベヤ・モータ・ロボット
直動・センサ・位置決め・ステージ
特注部品・図面加工部品
電気系
金型系
消耗品・補修用品・備品系
切削加工用品
-
切削工具
切削工具
-
エンドミル
-
フライスチップ・ホルダー
-
ヘッド交換式工具
-
自由指定直刃エンドミル
-
専用カッター
-
旋削チップ
-
旋削ホルダ
-
完成バイト・ロウ付けバイト
-
ローレット
-
ドリル
-
ドリル関連部品・用品
-
タップ
-
タップ関連部品・用品
-
ダイス
-
ダイス関連部品・用品
-
ねじ山修正・除去工具
-
タップ・ダイスセット
-
ねじ切りカッター
-
リーマ
-
面取りカッター
-
面取りカッター関連部品・用品
-
切削工具関連備品
-
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
-
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
-
磁気ボール盤カッター
-
ボーリングシステム
-
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
-
アングルヘッド
-
コレット
-
スリーブ・ソケット(ツーリング)
-
アーバ
-
ツーリング関連部品・用品
-
加工物基準位置測定器
-
芯出しバー
-
刃先位置測定器
-
ツールプリセッター
-
テストバー
-
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
-
クーラントライナー・クーラントシステム
-
エアージェット・エアークーラー
-
クーラント関連部品・用品
-
円テーブル・ロータリーテーブル
-
- 工作機工具・治具
生産加工用品
-
測定工具・計測機器
測定工具・計測機器
-
ノギス
-
pH計・導電率計
-
ノギス関連アクセサリ
-
マイクロメーター
-
検知管
-
ダイヤルゲージ
-
ダイヤルゲージ関連部品・用品
-
ピンゲージ
-
ピンゲージ関連部品・用品
-
ハイトゲージ
-
流量計
-
ハイトゲージ関連部品・用品
-
リングゲージ
-
デプスゲージ
-
シックネスゲージ・すきまゲージ
-
内径測定器
-
ゲージ
-
スコヤ
-
定規
-
コンベックス
-
巻尺
-
はかり
-
角度計
-
光学機器
-
水平器
-
レーザー測定器
-
マグネット関連
-
定盤
-
数取器・カウンタ
-
ガス測定器・検知器
-
ケガキ用品
-
ストップウォッチ・タイマー
-
テンションゲージ
-
環境測定器
-
温度計・湿度計
-
圧力計
-
顕微鏡
-
天秤・天秤関連品
-
分銅
-
硬度計
-
振動計・回転計
-
水質・水分測定器
-
粘度計
-
膜厚計・探知器
-
偏心測定器
-
表面粗さ測定器
-
音検出器
-
測定データ機器
-
アースメータ(接地抵抗計)
-
テスタ・マルチメータ
-
オシロスコープ
-
クランプメータ
-
検相器・検電器・導通チェッカ
-
絶縁抵抗計
-
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
-
安全試験器
-
回路素子測定器
-
信号源・ファンクションジェネレータ
-
電源装置
-
高周波測定器(RF測定器)
-
計測機器関連品
-
電圧計・電流計
-
電力計
-
その他電気計測器
-
- 放電加工用品
- 研削研磨・切断用品
-
手作業工具
手作業工具
-
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
-
六角棒レンチ
-
モンキーレンチ
-
トルクスレンチ
-
ソケットレンチ
-
トルクレンチ
-
トルクレンチ関連部品・用品
-
トルク測定器
-
ドライバー
-
ドライバー関連部品・用品
-
トルクドライバー
-
トルクドライバー関連部品・用品
-
プライヤー
-
プライヤー関連部品
-
ニッパー
-
ニッパー関連部品
-
ペンチ
-
ペンチ関連部品
-
ハンマー
-
工具セット・ツールセット
-
工具セット・ツールセット関連部品・用品
-
カッターナイフ
-
タガネ
-
ドライバービット
-
ドライバービット関連用品
-
プーラ
-
刻印・ポンチ
-
車輌整備用工具
-
水道・空調配管用工具
-
切断用工具
-
絶縁工具
-
板金用工具
-
防爆工具
-
かしめ工具
-
電設工具
-
バール・テコ
-
ソケットビット
-
ソケットアダプター
-
ピンセット
-
-
電動工具・空圧工具
- 小型加工機・卓上加工機
- 溶接用品
- はんだ・静電気対策用品
MRO・工場用副資材
メーカーから探す
特集から探す
株式会社放電精密加工研究所
購買依頼書を“運ぶ日々”に終止符
現場と管理部門、双方の負荷を軽減した新たな仕組み
企業プロフィール

- ・社名:
- 株式会社放電精密加工研究所
- ・創業:
- 1961年
- ・業種:
- 精密機械器具
- ・事業内容:
- 精密金属部品、金型、各種電極の製造および放電加工機の開発・販売
- ・従業員数:
- 733名(連結)/544名(単体)※2025年2月現在
- ・会社HP:
- https://www.hsk.co.jp/ja/index.html
放電加工技術をコアに、精密部品や金型の製造を手がける株式会社放電精密加工研究所。自動車・航空機・エネルギーといった幅広い産業領域において、独自の高精度加工技術で信頼を集めてきた。
同社の小牧工場では、製造現場で日常的に使用されるゴム手袋やペーパーウエスなどの消耗品について、紙の購買依頼書と手作業による在庫確認を中心とした運用が続いていた。業務の属人化や注文工数の増加、在庫切れリスクといった課題が積み重なるなかで導入されたのが、ミスミが提供する間接材トータルコストダウンサービス「MISUMI floow(フロー)」だった。
今回は小牧工場の製造課長T.Kさまと生産管理係長H.Hさまに、導入によって何が変わったのか、現場にどんな影響があったのか。導入の経緯とその後の手応えを中心にお話を伺った。

ー目次ー
-
導入前の課題
-
導入の決め手
-
導入後の効果
社内の反応 -
今後の展望
<導入前の課題>
紙の購買依頼書がもたらす“在庫切れ”のプレッシャー
放電精密加工研究所では、ゴム手袋やペーパーウエスなど、製造現場で日々大量に使用される消耗品の調達・管理において、紙ベースのアナログな注文フローを採用していた。現場での在庫確認から管理部門による注文まで、多くの工程が人手に依存しており、属人的な業務負荷や在庫切れのリスクが慢性的な課題となっていた。
T.Kさま:
以前は、消耗品を使う現場側が紙の購買依頼書を作成し、それを私が預かって管理部門に渡すという流れでした。依頼は毎日4~5枚、多い日で10枚ほど発生していました。各部署から依頼が集まってくるため、紙の受け渡しだけでも手間でした。自分でも「紙を運ぶゲームをしているみたいだな」と思うことがありましたね。
在庫管理については、毎週決まった曜日に現場担当者が在庫数を確認していました。現場作業を一時中断して数を数え、不足していれば手書きで購買依頼書に記入して、上長の押印をもらい提出するという運用でした。現場業務の合間におこなうには負担が大きかったと思いますし、依頼書は必ず私に来るため、私自身が伝達漏れを起こしてしまったこともありました。属人的なフローゆえに、どうしてもミスが起きやすい構造だったと思います。
H.Hさま:
仕入れはミスミ以外にも複数の企業からおこなっていたため、取引先ごとに異なる手段でやり取りしていました。その分管理部門の業務負荷は高く、注文作業だけで相当な時間を取られていたはずです。現場からの依頼は全て管理部門が捌くので、かなりの工数がかかっていましたね。
T.Kさま:
まとめて注文すれば手間も減らせるのですが、保管スペースに限りがあるため、少量ずつ高頻度で購入するしかありませんでした。その結果、注文回数がどうしても多くなってしまいます。在庫を切らしてしまって、他の部署から借りて急場をしのぐこともありました。
H.Hさま:
現場からは「仕組みを変えられないか」という声が出ていました。ただ、紙ベースでの運用が長年続いていたこともあり、なかなか改善に踏み切れないまま属人的な運用が続いていたのが実情です。使用実績や在庫の消費傾向も、全体を見渡して分析するのは難しい状況でした。
<導入の決め手>
現場起点の課題意識と他拠点での実績、“業務負荷を減らす手段”としての確信
「MISUMI floow」の導入は、グループ内の厚木工場での成功事例がきっかけだった。製造現場の業務効率化と、注文依頼の手間を減らしたいというニーズが重なり、現場と間接部門の双方で導入の必要性が高まっていた。導入にあたっては、在庫を持たない補充の仕組みや消費履歴の可視化といったサービス特性が評価され、社内説明を経て不安点をクリアしながら導入に踏み切った。
H.Hさま:
「MISUMI floow」の存在を知ったのは、グループ内の厚木工場での導入が先に進んでいたからです。「他拠点でも展開できるところがあれば紹介したい」と話が社内であったのですが、私の元上長が厚木工場にいて、「小牧工場でも合いそうだ」と声をかけてもらったのがきっかけでした。
T.Kさま:
現場目線で見ると、必要なときに必要なものを自販機で手に取れるというのは、とても助かる仕組みだと感じました。とにかく現場としては、消耗品が切れないことが何より大切です。また、それまでは毎日のように購買依頼書を作成・提出しなければならないという手間がありましたが、それが不要になると聞いて、大きな負担軽減になると感じました。
H.Hさま:
在庫を持たなくて済む、という点も非常に魅力的でした。実際にどれだけ使われているかの履歴がしっかり残るようになり、これまで属人的にカウントしていた在庫数を、仕組みでカバーできるという点は、有用なポイントと感じました。
導入前には、「どれだけ楽になるのかどうか見えにくい」という声も現場からは上がっていました。ただ、ミスミにお願いして社内で説明会を開いてもらい、導入の仕組みや実際の流れなどをしっかり話してもらいました。その結果、不安の声も少しずつ減っていきました。
間接部門の立場としては、製造現場の社員が本来の業務に集中できるように支援することが使命だと思っています。現場の手間を減らすことにつながるのであれば、積極的にこうした仕組みは取り入れていきたいと考えていました。

<導入効果・社内の反応>
万が一の在庫切れに備えなくていい、「必要なときに、すぐそこにある」環境へ
「MISUMI floow」の導入により、使用頻度が特に高い消耗品の管理が効率化された。紙への記入や注文の手間が大幅に削減されただけでなく、「在庫切れ」への不安が解消されたことで、現場では本来の業務に集中できる体制が整いつつある。現場の声や利用状況からも、作業効率や業務満足度の向上につながっている様子がうかがえる。
T.Kさま:
購入依頼書を記入する手間がなくなったのは大きな変化です。現場からも「すごく助かっている」という声が上がっています。必要なときにその場で使えるという安心感もありますし、個人的にも非常に助かっています。
H.Hさま:
これまで管理側では、日々多くの依頼書を受け取り、それを処理する作業が発生していましたが、その工数を大幅に削減できました。また、以前は「万が一の在庫切れに備えて」と、現場社員が“念のため”による過剰在庫を持つようなこともありましたが、今ではそういったことも必要なくなりました。補充はミスミが定期的に対応してくれるので、安心して運用を任せられます。その結果、消耗品の保管スペースが不要になり、物理的にも空きが生まれました。
T.Kさま:
導入によって、どの製品をどれだけ使ったか、どれだけ工数が削減されたかがダッシュボードで見えるようになりました。数値として見えると導入効果を実感できますし、次の改善にもつながると思います。
H.Hさま:
「MISUMI floow」の導入を機にアイテムの見直しも実施しました。 例えば、以前使用していた手袋は、10枚入りのうち2枚ほどが破損していて使えないということがありましたが、ミスミの製品に変えてからはそういった不良がなく、結果的に無駄が減って、コスト効率も上がっていると感じます。
自販機の操作面に関しては、ICカードでも顔認証でもどちらでも使えるので、現場にも自然と馴染んでいます。登録作業は最初に1回だけ済ませれば良いですし、特に大きなトラブルもなく使えています。

小牧事業所 小牧製造課 課長 T.Kさま
<今後の展望>
自販機データ活用で実現する製造現場のペーパーレス化と業務効率化
同社は次なるステップとして、現場ニーズを踏まえた製品ラインナップの拡充や、データを活用した業務改善に取り組み始めている。DX化が加速するなか、今回の導入を一つの成功事例と位置づけ、さらなる業務改善へと取り組みを広げている。
T.Kさま:
現在、自販機で取り扱っている品目はある程度固定されているのですが、現場からは「この商品も自販機で扱えないか?」という声が出始めています。やはり一度便利さを体感すると、「もっと活用できないか」という視点が自然と出てくるのだなと感じます。今後、より有益なアイテムがあれば前向きに検討していきたいと思っています。
H.Hさま:
実際の使われ方を見ていると、製品の入れ替えや棚割の見直しをおこなう必要性も感じています。どの製品がどれだけ使われているかがデータで見えるようになったことで、改善の根拠が持てるようになりました。「なぜこのサイズがよく使われているのか?」「作業内容の変化や使用頻度に理由があるのか?」といった部分まで掘り下げて考えられるようになり、単なる数量の把握にとどまらず、現場の作業実態や負荷まで踏み込んだ改善に活かしていきたいと考えています。
昨今、製造現場でもペーパーレス化が求められるようになっています。そういった中で、今回のような自販機による仕組みを導入できたことは、当社にとっても非常に有効な事例になったと感じています。今後も、他の領域でも同じように業務効率化を進めていければと考えています。

小牧事業所 小牧製造課 T.Mさま
<インタビュー協力>
株式会社放電精密加工研究所
小牧事業所 小牧製造課 課長
T.Kさま
株式会社放電精密加工研究所
小牧事業所 生産管理・営業課 生産管理係 係長
H.Hさま
株式会社放電精密加工研究所
の導入事例記事をダウンロードする
他の導入事例記事を見る