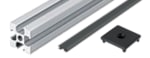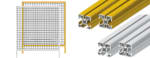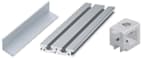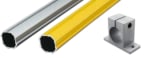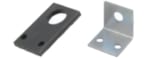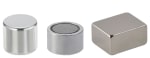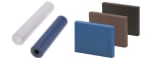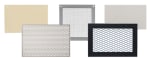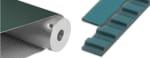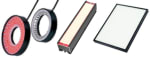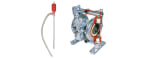(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
カテゴリ・メーカーから探す
メカニカル部品系
筐体・調整締結・素材
- フレーム・サポート部品・支柱
- キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品
-
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
-
六角穴付きボルト
-
脱落防止ねじ
-
貫通穴付ボルト
-
六角ボルト
-
小ねじ
-
止めねじ
-
座金組込みねじ
-
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
-
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
-
でんでんボルト
-
アイボルト
-
樹脂ねじ・セラミックねじ
-
全ねじ・スタッドボルト
-
いたずら防止ねじ
-
配管Uボルト
-
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
-
マイクロねじ・微細ねじ
-
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
-
ドリルねじ
-
四角ボルト・丸ボルト
-
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
-
座金(ねじ用ワッシャ)
-
ナット
-
アンカーボルト
-
リベット・鋲
-
インサート
-
建材用スクリュー
-
ねじ用工具類
-
ワッシャ・カラー
-
シム
-
スナップピン・割りピン
-
マシンキー
-
止め輪・リング
-
スクリュープラグ
-
アジャスタ
-
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
-
-
ばね・アブソーバ・調整締結・ピン・小物部品
-
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
-
対策・メンテナンス関連
空圧・油圧・配管・温調部品
回転伝達・コンベヤ・モータ・ロボット
直動・センサ・位置決め・ステージ
特注部品・図面加工部品
電気系
金型系
消耗品・補修用品・備品系
切削加工用品
-
切削工具
切削工具
-
エンドミル
-
フライスチップ・ホルダー
-
ヘッド交換式工具
-
自由指定直刃エンドミル
-
専用カッター
-
旋削チップ
-
旋削ホルダ
-
完成バイト・ロウ付けバイト
-
ローレット
-
ドリル
-
ドリル関連部品・用品
-
タップ
-
タップ関連部品・用品
-
ダイス
-
ダイス関連部品・用品
-
ねじ山修正・除去工具
-
タップ・ダイスセット
-
ねじ切りカッター
-
リーマ
-
面取りカッター
-
面取りカッター関連部品・用品
-
切削工具関連備品
-
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
-
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
-
磁気ボール盤カッター
-
ボーリングシステム
-
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
-
アングルヘッド
-
コレット
-
スリーブ・ソケット(ツーリング)
-
アーバ
-
ツーリング関連部品・用品
-
加工物基準位置測定器
-
芯出しバー
-
刃先位置測定器
-
ツールプリセッター
-
テストバー
-
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
-
クーラントライナー・クーラントシステム
-
エアージェット・エアークーラー
-
クーラント関連部品・用品
-
円テーブル・ロータリーテーブル
-
- 工作機工具・治具
生産加工用品
-
測定工具・計測機器
測定工具・計測機器
-
ノギス
-
pH計・導電率計
-
ノギス関連アクセサリ
-
マイクロメーター
-
検知管
-
ダイヤルゲージ
-
ダイヤルゲージ関連部品・用品
-
ピンゲージ
-
ピンゲージ関連部品・用品
-
ハイトゲージ
-
流量計
-
ハイトゲージ関連部品・用品
-
リングゲージ
-
デプスゲージ
-
シックネスゲージ・すきまゲージ
-
内径測定器
-
ゲージ
-
スコヤ
-
定規
-
コンベックス
-
巻尺
-
はかり
-
角度計
-
光学機器
-
水平器
-
レーザー測定器
-
マグネット関連
-
定盤
-
数取器・カウンタ
-
ガス測定器・検知器
-
ケガキ用品
-
ストップウォッチ・タイマー
-
テンションゲージ
-
環境測定器
-
温度計・湿度計
-
圧力計
-
顕微鏡
-
天秤・天秤関連品
-
分銅
-
硬度計
-
振動計・回転計
-
水質・水分測定器
-
粘度計
-
膜厚計・探知器
-
偏心測定器
-
表面粗さ測定器
-
音検出器
-
測定データ機器
-
アースメータ(接地抵抗計)
-
テスタ・マルチメータ
-
オシロスコープ
-
クランプメータ
-
検相器・検電器・導通チェッカ
-
絶縁抵抗計
-
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
-
安全試験器
-
回路素子測定器
-
信号源・ファンクションジェネレータ
-
電源装置
-
高周波測定器(RF測定器)
-
計測機器関連品
-
電圧計・電流計
-
電力計
-
その他電気計測器
-
- 放電加工用品
- 研削研磨・切断用品
-
手作業工具
手作業工具
-
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
-
六角棒レンチ
-
モンキーレンチ
-
トルクスレンチ
-
ソケットレンチ
-
トルクレンチ
-
トルクレンチ関連部品・用品
-
トルク測定器
-
ドライバー
-
ドライバー関連部品・用品
-
トルクドライバー
-
トルクドライバー関連部品・用品
-
プライヤー
-
プライヤー関連部品
-
ニッパー
-
ニッパー関連部品
-
ペンチ
-
ペンチ関連部品
-
ハンマー
-
工具セット・ツールセット
-
工具セット・ツールセット関連部品・用品
-
カッターナイフ
-
タガネ
-
ドライバービット
-
ドライバービット関連用品
-
プーラ
-
刻印・ポンチ
-
車輌整備用工具
-
水道・空調配管用工具
-
切断用工具
-
絶縁工具
-
板金用工具
-
防爆工具
-
かしめ工具
-
電設工具
-
バール・テコ
-
ソケットビット
-
ソケットアダプター
-
ピンセット
-
-
電動工具・空圧工具
- 小型加工機・卓上加工機
- 溶接用品
- はんだ・静電気対策用品
MRO・工場用副資材
メーカーから探す
特集から探す
- 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
ミスミ測定工具・計測機器の校正
ミスミ取り扱いの測定工具・計測機器における校正証明書についてご紹介します。
校正のお申し込みをご検討の際にご活用ください。
- ミスミ測定工具・計測機器の校正対応可能な校正証明書の種類について
解説しています。 - 測定工具・計測機器
校正証明書付き商品校正付き商品をご希望の場合は
こちらをご覧ください。 - ミスミ校正サービスお手持ちの工具・機器の再校正について
ご紹介しています。
校正とは
「標準機を用いて測定工具の表す値と、その真の値との関係を求める作業」と定義されています。
合否判定はともなわず、校正した測定工具が使用可能かどうかは、その測定工具の所有者が行うこととなります。
ISO9001国際規格では測定工具に関し、「定められた間隔または使用前に、国際または国家計量基準にトレース可能な計量基準に照らして校正または検証する」とされており、常に信頼性が確保された測定値が要求されています。また校正を行う期間(周期)は定められていませんが、定期的に行うのが原則とされるため1年に1回の校正が推奨されています。
なお、校正は器差のズレを確認することであり、計測機器の現状把握と確認をする作業です。修理やメンテナンスではないため、ズレや機能を改善することはできません。
※ミスミでは修理、メンテナンスはお受けしておりません。
校正種類について
校正には、一般校正とJCSS校正があります。
一般校正
一般校正とは国家計量標準にたどりつく標準器を使用して、第三者機関が校正試験を実施し、値の結果を比較する作業と、その比較結果を記録することです。一般校正で用いた標準器により校正を行ったことの証明が記された書面を「校正証明書」、一般校正において用いた標準器と国家標準との繋がりが記された書面を「トレーサビリティ体系図」、標準器との比較結果が記された書面を「試験成績書」と呼びます。ミスミサイトで掲載中の測定工具や計測機器で校正付きで販売している商品、またお手持ちの測定工具、計測機器を再校正する場合の校正は、一般校正です。校正を実施し証明書を発行する機関は商品ごとに異なります。
一般校正で発行される書面の一例
①校正成績表
校正成績表には、以下の内容を記載いたします。
1. 発行No. 2. 校正機関名 3. 校正年月日 4. 校正項目
5. 被校正機器 ①品名 ②型番 ③製造者 ④製造番号 ⑤校正点 ⑥校正結果データ ⑦特記事項
②校正証明書
校正証明書には、以下の内容を記載いたします。
1. 発行No. 2. 依頼者名 3. 被校正機器の品名、型番、製造番号、製造者 4. 校正機関名
5. ISOの要求事項である校正が国家標準にトレーサブルで あることの証明の宣言文
6. 校正に使用した標準器の管理番号、品名、製造者、機器番号 7. 校正証明書の発行日 8. 標準温度
③トレーサビリティ体系
トレーサビリティ体系には、以下の内容を記載いたします。
1. 被校正機器の品名 2. 被校正機器を校正した標準器が国家標準機関などにトレースするまでの経路をチャートに表した体系図
3. トレーサビリティ体系の発行日 4. 校正機関名
④上記文書3点セット
校正成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系3点セットです。ISO監査においてはこの3点の文書が必要となります。

JCSS校正
JCSS認定を受けた校正事業者の発行するJCSS標章付校正証明書は、その校正結果が国家計量標準へのトレーサビリティ(つながり)があること、また、校正事業者の技術能力があることを公に証明しているものです。したがって、JCSS標章付校正証明書付の標準器は、国際または国家計量標準にトレーサブルであることが確認されています。
ISO9001の審査における測定工具の「校正または検証」や、試験所認定などのトレーサビリティの要求事項をクリアすることができます。JCSS標章付校正証明書がある場合、校正成績書、校正証明書トレーサビリティ体系図は不要です。
JCSSとは
計量法第8章の規定により、軽量のトレーサビリティ確保のために設立された制度で、測定工具を校正する事業所の技術能力とやトレーサビリティが、校正機関認定の国際規格ISO/IEC17025(JIS17025)の基準を満たしていることを、認定機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター(略称IAJapan)が審査・認定する校正事業者登録制度をいいます。
※JCSSとは…Japan Calibration Service Systemの略称、軽量法校正事業者登録制度をいいます。
JCSS標章付校正証明書の一例

ポイント
-
一般校正
- 標準機を使用して第三者機関が行う校正
- 校正証明書は3種類の文書から構成される
-
JCSS校正
- JCSS認定を受けた事業者が行う校正
- 校正証明書は1種類のみ
よくあるご質問
- Q トレーサビリティの確保とは?
-
A
JIS Z8103にはトレーサビリティとは「標準器、計測器がより高位の測定標準によって次々と校正され、国家基準・国際基準につながる経路が確立されていること」となっており、
使用する計測機器がより上位の標準器により校正され、 その標準器はさらに上位の標準器で校正され、最終的には国家基準・国際基準につながっていることです。
ISO9000 の要求事項「検査・測定及び試験装置の管理」では計測機器を社外校正する場合は、その社外校正先より成績書はもちろんトレーサビリティが確保されている
証明(校正証明書、トレーサビリティ体系図など)を確認・入手し、記録として残す必要があります。 - Q 計測機器の管理精度はどのように決める?
-
A
使用する計測機器の管理精度は測定項目、測定対象の必要精度、計測機器自体の精度を明確にしたうえで決定しなければなりません。
即ち、測定、検査する被測定対象物がどのような状態(形状、硬さ…)か、製品規格上の許容差はいくらか、また、計測機器の精度は、使用環境条件は、使用者の技術レベルは…
などをひとつずつ確認し決定しなければなりません。 従来から被測定対象の必要精度の1/10くらいといわれていますが、米のANS規格では1/4が規定されています。
ただし、コスト面から常識的には1/3相当以上で良いと考えます。それでも困難な場合は補正したり、計測回数を多くして平均するような方法もあります。
なお、実際には過去の校正結果データーにより決めたり、新たに校正を行いその校正結果データーにより決めたり、経験者の判断により管理精度を決めている例も多いようです。
必要以上(例えば、購入した計測機器の精度仕様)に管理精度を厳しくすると精度維持にコストがかかり経済的にも大変です。 - Q 計測機器の校正周期はどのように決める?
-
A
計測機器の校正周期は、企業で生産される製品品質を決定する管理精度とともに重要な要素です。その周期の決定方法には、JIS Z 9090-1991「測定-校正方式通則(付属書1)」の
論理的算出方法もありますが、よく使用されているISO10012-1規格「付録A測定装置の間隔決定のためのガイドライン」の方法の考え方の一例を説明します。
まず、計測機器を扱った経験があり機器仕様を熟知した人が、使用頻度・使用環境条件および要求される精度を考慮して決定し(規格では技術的直感といっている。)
次に決定した周期を、蓄積した校正結果データー(3回以上は必要)をもとに、校正費用にかかるコストと製品品質への影響の危険度から周期の延長、短縮をする方法です。
ただし、計測機器による「不良発生によるコスト」は「計測機器校正費用」に比べて遥かに大きくて社会的な影響が計り知れないことを考え慎重に決定することが必要となります。
また、それが品質管理、計量管理に携わっている者の手腕でもあります。 - Q QS9000における計測機器の管理はどのようなことが必要?
-
A
QS9000とはご存知のようにISO9000シリーズ(以下ISO9000s)では飽き足らなくなった(不十分だと考えた)自動車メーカーであるアメリカのビッグ
3(クライスラー、フォード、GMの3大自動車メーカー)がALAG(自動車産業アクショングループ)というひとつの共同チームを作り、ISO9000sをベースに作った規格です。
計測機器の管理に関していえばISO9000sはご承知のように、文書類がそろっていればパスします。技能のチェックが入っていません。それがもの足りないということです。
広い意味でいえば技能についての条項はISO9000にも入っているのですが、厳密な意味では技能の追求はされていません。それで、QS9000を作ったということです。
QS9000規格の中の4.11.2.b.1項が校正・試験に関する規定で、ここでISO/IEC17025(ガイド25の改定版)に適合した校正機関を使うこととされています。日本国内ではそれに満足する機関は、現在のところ計量法トレーサビリティ制度の認定事業者か、JABでの17025を認定された数社(いずれも、ある要素・範囲に限定)しかありません。