近接センサとは
近接センサは、検出物体が近づいたら、その旨を非接触の状態で検出することのできるセンサです。
リミットスイッチやマイクロスイッチなど、従来の接触で検出する方式の代替手段として用いることができます。
具体的には、配管経路をコントロールしているバルブの開閉チェックや、工場でのタンク内容量の検知、製品の異物混入の検知などでの活用が可能です。
近接センサは対象物の移動情報や存在情報を電気信号に置き換えることで非接触での検出を可能としており、“汎用タイプ”と“アルミ検出タイプ”の2種類があります。
それぞれの原理については以下をご参照ください。
近接センサの種類
| 汎用タイプ |
検出コイルから高周波磁界が発生し、この磁界に金属の検出物体が近づくと、電磁誘導により検出物体に誘導電流が流れる。
誘導電流によって、コイルへの電流の流れにくさを示す“インピーダンス”が変化し、発振が停止することで物体を検出する。 |
| アルミ検出タイプ |
非磁性体(磁石にくっつきにくい物体)が近づくと、高周波発振の周波数が変化する。
この変化を観測することで物体を検出する。 |
上記を見るとわかるように、いずれの方式であっても近接センサでは検出できる物体の種類が決められています。
そのため、上記に該当しない物体を扱いたい場合には、後述する光電センサなど、ほかのセンサを選びましょう。
なお、近接センサには、検出物体に接触しない仕組みならではのメリットがあります。
近接センサのメリット
- 検出物体が摩耗する心配がない
- 検出物体の汚れや油、水、表面の色の影響を受けない
- 接触式のスイッチよりも応答速度が速い
- 対応している温度の範囲が広い
近接センサでは、検出時にセンサと物体が直接触れ合わないため、検出物体が摩耗することがありません。
また、検出物体の表面が濡れていたとしても、非接触ゆえにセンサへの影響がないのもうれしいポイントです。
ただし非接触ゆえに、温度や別のセンサなど、周囲の環境を受けやすいという点にはご注意ください。
スタンダードタイプ近接センサ E2E

近接センサをお探しの方に最初に手に取っていただきたいスタンダードタイプです。条件に合わせて最適な機種を選択可能なワイドバリエーションで、優れた環境耐性を実現しました。コードプロテクタを標準採用して断線対策を施しています。
| 商品情報 |
| メーカー |
オムロン |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
磁性金属 |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
2~4mm±10%、7~8mm±10%、10mm±10%、
14mm±10%、20mm±10% |
| 出力方式 |
コード引き出しタイプ、コネクタタイプ、コネクタ中継タイプ |
| 保護構造 |
コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプ:IEC規格 IP67
コネクタタイプ:IEC規格 IP67 |
| 使用周囲温度 |
動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
| 本体重量 |
約15~175g |
| レビュー(☆) |
4.8 |
スタンダードタイプ近接センサ E2Eの詳細はこちら
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

M12で7mmの世界最長検出距離で近接センサとの衝突を回避し、設備を安定稼働させられます。また、検出余裕度も向上し、ドグが離れても安定して検出します。誰にでも簡単に交換できる調整レス仕様で、約10秒で交換できます。
| 商品情報 |
| メーカー |
オムロン |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
- |
| 検出対象 |
- |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
3mm、7mm、10~11mm |
| 出力方式 |
コード引き出しタイプ、コネクタタイプ、コネクタ中継タイプ |
| 保護構造 |
コード引き出し/コネクタ中継:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1) |
| 使用周囲温度 |
動作時、保存時-25~+70℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.5 |
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXTの詳細はこちら
光電センサとは
光電センサは、可視光線や赤外線といった光を発射し、それが反射したり遮られたりしたときの光量の変化によって、検出物体の有無や表面の状態などを確認できるセンサです。
たとえば、製造の現場では色の濃淡やワーク表面の凹凸を検出する、といった用途で使われています。
なお、光電センサには光を出す“投光部”と光を受ける“受光部”があり、この2つを使って物体を検出する仕組みは6種類に分かれます。
それぞれの仕組みや特長については以下をご覧ください。
光電センサの種類
| 名称 |
構造 |
仕組み・特長 |
| 透過型 |
投光器と受光器に分かれている |
投光器から受光器に向かって出される光を物体が遮ることで検出する。
不透明体であれば形状・色・材質に関係なく検出できる。 |
| 回帰反射型 |
1つのセンサに投光部と受光部がある |
投光部から出た光が、反射板や反射テープに跳ね返され、その光を物体が遮ることで検出する。
狭いスペースへの設置が可能で、不透明体であれば形状・色・材質に関係なく検出できる。 |
| 拡散反射型 |
投光部から物体に光を照射し、物体から反射された光を受光部で受けて検出する。
狭いスペースへの設置が可能で、反射体であれば透明体でも検出できる。 |
| 限定反射型 |
仕組み自体は拡散反射型と同じである。
投光部と受光部に角度がついていることにより、それぞれの光軸が交差する範囲内にある物体のみを検出できる。
微妙な段差や小さな凹凸の検出が可能。 |
| 距離設定型 |
投光部から検出物体に光を照射し、反射光の角度で“あらかじめ設定した位置からの距離”を判断する。
小さな物体でも高い精度で検出できる。 |
| 光沢度判別用反射型 |
投光部から検出物体に光を照射し、正反射と拡散反射の差から、物体の光沢度を判断する。
色の影響を受けず、透明体でも検出できる。 |
上記を見るとわかるように、光電センサのなかには、物体の距離を測る距離設定型や光沢度を測る光沢度判別用反射型など、特定の用途に特化したものもあります。
検出できる物体は光電センサの種類によって異なりますので、検出物体と用途を明確にしたうえで適切な種類を選びましょう。
なお、光電センサを利用するメリットとしては以下に整理した内容が挙げられます。
光電センサのメリット
- 非接触のため物体にもセンサにも傷がつかない
- 検出距離が長い
- 応答時間が短い
- さまざまな素材の物体を検出できる
物体に直接触れずに検出を行うため、物体もセンサも摩耗することがないのは、近接センサと同じです。
そのうえで光電センサならではのメリットとして挙げられるのは、光の反射を利用しているので検出距離が長く、さらに応答時間が非常に短いという点です。
たとえば10m以上など、磁気や超音波を使ったセンサでは届かないような距離でも光電センサなら検出できますし、時間もかかりません。
また、金属の検出のみに対応している近接センサと異なり、ガラスやプラスチック、木材、あるいは液体など、光を反射する物体であれば基本的に検出することができます。
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

透過形30m、回帰反射形4m、拡散反射形1mの長距離型でスタンダードタイプの光電センサです。光軸と機械軸のズレは±2.5°以内で光軸調整が簡単に行えます。独自の外乱光回避アルゴリズムで高い安定性を実現しました。
| 商品情報 |
| メーカー |
オムロン |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
- |
| 検出対象 |
φ12mm以上の不透明体、φ75mm以上の不透明体 |
| 検出方式 |
透過形、拡散反射形、回帰反射形 |
| 検出距離 |
透過形:10m、15m、30m
拡散反射形:90±30mm、100mm、1m
回帰反射形:3m、4m |
| 出力方式 |
標準タイプ:コード引き出しタイプ(標準コード長2m/500mm)/M8コネクタタイプ
防油タイプ:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M12コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)、M8コネクタタイプ |
| 保護構造 |
IEC規格 IP67 |
| 使用周囲温度 |
動作時:-25~+55℃(結露および凍結しないこと)
保存時:-40~+70℃(結露および凍結しないこと) |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1000V 50/60Hz 1min |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.2 |
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zの詳細はこちら
ファイバユニット E32

豊富な形状でさまざまな設置スペースに対応する、耐環境タイプのファイバーユニットはお客さまのニーズにお応えします。光学技術を駆使し、検出確実性を向上しました。
| 商品情報 |
| メーカー |
オムロン |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
- |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.4 |
ファイバユニット E32の詳細はこちら
エリアセンサとは
透過型の光電センサのなかでも、主に製造現場に設置し、障害物や落下したワークの検出などに使うセンサをエリアセンサといいます。
LEDが縦に並んだ細長い形状の投光器と、同じ形状の受光器の2つを1つのセットとして使います。
通常、投光器から受光器に向かって真っすぐに光が照射されますが、そのあいだを障害物が通ると光が遮られるので、表示灯に色がついてアラートされるという仕組みです。
なお、エリアセンサは商品によって、LED同士の間隔を示す“光軸間距離”が異なります。
小さな物体を検出したい場合は光軸間距離が短いものを、反対に大きな物体を検出したい場合は光軸間距離が長いものを選ぶとよいでしょう。
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

幅30mm、厚さ13mmの超薄型・コンパクトサイズを実現。装置にフィットし、作業の邪魔になりません。また検出幅は6つのバリエーションがあり、最大検出幅540mmとさまざまなニーズに対応できます。
| 商品情報 |
| メーカー |
Panasonic |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
φ30mm以上の不透明体 |
| 検出方式 |
透過型 |
| 検出距離 |
5m |
| 出力方式 |
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、
PNPトランジスタ・オープンコレクタ |
| 保護構造 |
IP40(IEC) |
| 使用周囲温度 |
-10~+55℃(結露および凍結しないこと)、
保存時:-10~+60℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 |
| 本体重量 |
350~650g |
| レビュー(☆) |
4.0 |
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)の詳細はこちら
エリアセンサ BWシリーズ

最大10万㏓の使用周囲照度で、太陽光および白熱灯による誤作動はもちろん、高感度センシング性能により、雨水やホコリ等の影響を最小化できます。本製品は、最大7mの長距離検出と共に、光軸数、光軸ピッチ、そして検出幅によって計22種の多様なモデルを提供するだけでなく、相互干渉防止機能、自己診断機能等を内蔵して検出の信頼性を高め、高輝度表示灯で動作確認を容易にし、ユーザーの利便性が向上しました。
| 商品情報 |
| メーカー |
AUTONICS(オートニクス) |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
不透明体 |
| 検出方式 |
透過型 |
| 検出距離 |
0.1 ~ 7.0m |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
IP65 (IEC 規格) |
| 使用周囲温度 |
-10~55 ℃, 保存時: -20~60 ℃(結露および凍結しないこと) |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
充填部とケース間:1,000 VAC~ 50 / 60 Hzにて1分間 |
| 本体重量 |
1.4 kg |
| レビュー(☆) |
3.5 |
エリアセンサ BWシリーズの詳細はこちら
エリアセンサ BWPシリーズ

投光周波数選択による相互干渉防止機能により同級最高水準の検出信頼性を実現し、多様な製品群でユーザーが希望する環境によって幅広く使用することができます。また、自社開発のフレネルレンズとプラスチックケースを適用した超薄型デザイン設計で空間制約を最小化しました。
| 商品情報 |
| メーカー |
AUTONICS(オートニクス) |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
φ30mm以上の不透明体 |
| 検出方式 |
透過形 |
| 検出距離 |
0.1~5m |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
IP40 |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.0 |
エリアセンサ BWPシリーズの詳細はこちら
小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)

設置が可能なライターサイズのセンサ。部品箱のわずかなスペースにも取り付けが可能です。明るく見やすい作業表示灯を搭載し、離れたところからでもスムーズに確認できます。
| 商品情報 |
| メーカー |
Panasonic |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
φ29mm以上の不透明体(完全遮光物体) |
| 検出方式 |
透過 |
| 検出距離 |
30~300mm |
| 出力方式 |
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、
PNPトランジスタ・オープンコレクタ |
| 保護構造 |
IP62(IEC)、防滴形 |
| 使用周囲温度 |
-10~+55℃(結露および凍結しないこと)、
保存時:-20~+70℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 |
| 本体重量 |
投・受光器各約50g |
| レビュー(☆) |
4.5 |
小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)の詳細はこちら
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)

2線式の負荷電流を低電流化した無接点オートスイッチの直接取り付けタイプです。接点がないため作動回数に依存せず、寿命が長持ちします。全ての型で耐屈曲コードを使用しています。
| 商品情報 |
| メーカー |
SMC |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
- |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
NPNタイプ、PNPタイプ |
| 保護構造 |
IEC60529規格IP67 |
| 使用周囲温度 |
-10~60℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1500V1分間(リード線、ケーズ間)、
AC1000V1分間(リード線、ケーズ間) |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.4 |
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)の詳細はこちら
漏液センサとは
漏液センサは、薬液や純水といった液体が漏れていることを検出するセンサです。
また、その仕組みを応用して結露を検出することもできます。
漏液センサで液体の漏れを検出できる原理は、光電センサと同じ仕組みによるものです。
センサ本体に投光部と受光部があり、通常は投光部から発せられた光を受光部で受け取ります。
しかし、液体が漏れてセンサに触れると光の反射率が変わるので、受光部に届く光の量が減ります。
それを検知するとLEDの色が変わり、漏液を知らせるアラートとなるのです。
アンプ内蔵漏液センサ

吸紙不要で酸・アルカリ系薬液やIPA、純水、フロリナート、ガルデンなどさまざまな液体に対応する漏液センサです。本体側に動作表示灯があるため、スイッチの状態が一目で確認できます。取り付けはロック機構付きで、漏液検出後は県検出面をふき取るだけで再立ち上げが迅速に行えます。
| 商品情報 |
| メーカー |
アズビル |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
水 |
| 検出方式 |
反射形 |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
NPNオープンコレクタ、PNPオープンコレクタ |
| 保護構造 |
IP67(IEC規格) |
| 使用周囲温度 |
-25~+50℃(結露および凍結しないこと) |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 |
| 本体重量 |
約55g |
| レビュー(☆) |
5.0 |
アンプ内蔵漏液センサの詳細はこちら
マイクロフォトセンサとは
光電センサとよく似たセンサとして、マイクロフォトセンサが挙げられます。
マイクロフォトセンサも光電センサと同じく、光を利用して物体を検出するという仕組みで、透過型と反射型の2種類があります。
光電センサと異なるのは、マイクロフォトセンサのほうが小型で、なおかつ柔軟な利用が可能である点です。
マイクロフォトセンサならではの強みを以下にまとめました。
マイクロフォトセンサのメリット
- 繰り返し精度が高い
- 光電センサよりも安価である
- 形状のバリエーションが多く、さまざまな方向に取り付けられる
- 微弱な光を検出する能力が高い
特に、同一の条件下で繰り返し測定を行ったときのバラつきを示す“繰り返し精度”の数値がミクロンと非常に小さい、つまり精度が高い点が大きな強みとして挙げられます。
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)

小型化・省スペース化に貢献する超小型タイプのセンサです。電源逆接続保護回路、出力逆接続保護回路、出力短絡保護回路の3つの保護回路付きで、誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減します。入光時に点灯する大型動作表示灯(橙色)を搭載し、真横からも確認できます。
| 商品情報 |
| メーカー |
Panasonic |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
不透明体 |
| 検出方式 |
透過形 |
| 検出距離 |
6mm |
| 出力方式 |
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、
PNPトランジスタ・オープンコレクタ |
| 保護構造 |
IP64(IEC) |
| 使用周囲温度 |
-25~+55℃(結露および凍結しないこと)、
保存時:-30~+80℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 |
| 本体重量 |
10g、30g |
| レビュー(☆) |
4.0 |
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)の詳細はこちら
光電マイクロセンサ BS5シリーズ

計8種類の外形(K、T、L、Y、V、F、R、TA型)を有し、設置環境に合わせて選択できます。段差を最小化したデザインで異物による誤作動を最小化し、色々な方向より確認できる動作表示灯により視認性を確保しました。
| 商品情報 |
| メーカー |
AUTONICS(オートニクス) |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
不透明体 0.8×1mm以上 |
| 検出方式 |
透過形(非変調) |
| 検出距離 |
5mm |
| 出力方式 |
NPNオープンコレクタ |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.4 |
光電マイクロセンサ BS5シリーズの詳細はこちら
流量センサとは
流量センサでは、液体または気体の流量を測ることができます。
一定期間の流量を監視したり、あるいは総流量を連続的に監視したりすることができ、ほかの装置と連動させれば、一定の値でポンプの作動・停止などを行うことも可能です。
なお、流量センサは仕組みの違いによって以下の2種類に分けられます。
流量センサの種類
| 磁気誘導式 |
導電性のある液体の検知に使う。
液体が流れると、磁場が乱れて電圧が発生する。
その電圧の変化をもとに、液体の流量を計算する。 |
| パドルホイール式 |
気体や液体が“パドル”とよばれる部品に当たるとパドルが回転する。
その回転速度をトランスミッターやコントローラに送り、流量を測定する。
動きが速ければ速いほど、液体の流れを正確に読み取ることができる。 |
導電性のある液体の流量を検知したい場合は磁気誘導式、それ以外の場合はパドルホイール式を選ぶとよいでしょう。
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

3色表示・2画面表示対応モデルで従来製品と比べて40%の小型化を実現しました。設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転可能にし、操作性と視認性を向上させました。可動域は反時計回り90°、時計回り225°です。
| 商品情報 |
| メーカー |
SMC |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
水およびエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s〔3cP〕以下) |
| 検出方式 |
カルマン渦式 |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
IP65 |
| 使用周囲温度 |
0~50℃(結露および凍結しないこと) |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
195~1,075g |
| レビュー(☆) |
- |
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズの詳細はこちら
圧力センサとは
液体や気体の圧力を検知することができるのが、圧力センサです。
多くの圧力センサには、流体の圧力を感知したうえで電気量に変換する機能があるため、“圧力変換器”とよばれることもあります。
なお、圧力センサは“何の圧力を測定するのか”によって適したものが異なっており、それぞれ仕組みも分かれています。
圧力センサの種類
| 抵抗膜方式 |
圧力によって変形する、対象物のひずみを“電気抵抗の変化”として検知する。 |
| 静電容量方式 |
板状の素材が圧力でたわみ、それによって変化した静電気容量を測定する。 |
| 圧電素子方式 |
“ピエゾ素子”とよばれる、圧力を電圧に変換する素子を使って測定する。 |
| 光学方式 |
圧力を受けてゆがんだ光ファイバーから送られる光を、圧力に変換して計測する。 |
なお、圧力センサは単に圧力を計測できるものだけでなく、気圧に対する差や基準値からの変化を測定できるものもあります。
さまざまな種類の製品があるので、用途に合うものをお選びください。
ワイドレンジ真空計 CC-10

大気から超高真空を1つの真空計でまとめて計測可能で利便性が向上しました。接続するだけで圧力が表示されるため、操作不要で誰でも簡単に使用できます。クリーニングや交換などのメンテナンスも簡単です。
| 商品情報 |
| メーカー |
ビスタ |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
- ●大気圧から超高真空の圧力計測、圧力の遠隔表示と制御
|
| 検出対象 |
- |
| 検出方式 |
大気圧および荒引き圧力計測に水晶真空センサ使用、高真空計測にデュアルインバーティドマグネトロン方式のコールドカソードゲージを使用、センサを圧力レンジにより自動切り替え |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
保管時:-40℃~+55℃ 動作時:周囲温度 max 50℃
ベーキング温度: 制御回路部を外しセンサ単体にて150℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
700g |
| レビュー(☆) |
- |
ワイドレンジ真空計 CC-10の詳細はこちら
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](/pr/kw_select/sensor/img/item_15.png)
旧シリーズと比較し、くっきりと見やすいデジタル表示部になりました。消費電力を14%削減し、環境負荷を低減。また、2画面表示にしたことで、しきい値を画面モード切替の必要なくダイレクトに操作できます。
| 商品情報 |
| メーカー |
Panasonic |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
非腐食性気体 |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
IP40(IEC) |
| 使用周囲温度 |
-10~+50℃(結露および凍結しないこと)、保存時:-10~+60℃ |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
-10~50℃ |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.5 |
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)の詳細はこちら
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

汎用流体用圧力センサPSE560シリーズは、空気・非腐食性ガス・不燃性ガスと幅広い流体応適応した圧力センサです。電圧/電流のアナログ出力に対応しています。
| 商品情報 |
| メーカー |
SMC |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
アナログ出力 |
| 保護構造 |
IP40 |
| 使用周囲温度 |
動作時:0~+50℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと) |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
AC1,000V 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間 |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
- |
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズの詳細はこちら
温度センサとは
温度センサはその名の通り、物体や液体、気体などの温度を測定するセンサのことです。
詳細な分類を以下に整理しました。
温度センサの分類
| 非接触式 |
熱型 |
| 量子型 |
| 接触式 |
電気式 |
測温抵抗体(RTD) |
| リニア抵抗器 |
| サーミスタ(PTC/NTC) |
| 熱電耐 |
| IC温度センサ |
| 機械式 |
感温フェライト |
| 熱膨張型 |
非接触式の温度センサは、輝度や音、赤外線強度などで温度を測定するセンサです。
近年は、簡易式の体温計などによく用いられています。
気体や液体の温度を測る場面では、基本的には接触式の温度センサが使われています。
なかでも、よく用いられるのは電気式のうち、測温抵抗体とリニア抵抗器、サーミスタの3種類です。
以下では、この3つの特長を解説いたします。
非接触式・電気式の温度センサの種類
| 測温抵抗体(RTD) |
白金やニッケル、銅などの金属を使用して温度を測る。
特に白金は安定性や直線性に優れており、広い温度範囲をカバーすることができる。 |
| リニア抵抗器 |
ニッケルやパラジウムの合金を使用して温度を測る。
白金ほどは精度が高くないが、さまざまな抵抗値から選ぶことができる。 |
| サーミスタ(PTC/NTC) |
温度によって抵抗値が変化する素子(サーミスタ)を使用して温度を測る。
温度が上がると抵抗値が上がるPTCタイプと、抵抗値が下がるNTCタイプがある。
小型かつ高い感度での測定ができる。 |
それぞれ長所と短所が異なりますので、利用シーンに合うものを選びましょう。
温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

デジタル温度コントローラmonoOne(モノワン)にお使いいただける先端溶接タイプのK熱電対です。K熱電対に対応しているその他の温度調節器にもご使用いただけます。熱電対素線にフッ素樹脂やガラス繊維などの被覆を施しており、保護管などに入れずにそのまま使用できます。
| 商品情報 |
| メーカー |
スリーハイ |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
温度 |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
- |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.5 |
温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプの詳細はこちら
温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

絶縁シート上に熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適した薄型のK熱電対温度センサです。レスポンスタイムが速く、高温用接着剤などでの貼り付けも可能です。
| 商品情報 |
| メーカー |
スリーハイ |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
- ●デジタル温度コントローラ monoOne®-120や他の温度調節器の表面温度測定
- ●実験温度計測など
|
| 検出対象 |
温度 |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
200℃ |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.2 |
温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)の詳細はこちら
温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

熱電対Kシースタイプは、熱電対素線を通したステンレスシース管中に無機絶縁物を高圧で充填したもので、耐振性・柔軟性・高寿命を求められる環境に適した製品のため、経済性に優れています。ガラス被覆、シリコン被覆の2種類があり、ケーブル部分の柔らかさと被覆材耐熱温度が異なりますので、ご希望条件に合わせてご選定いただけます。
| 商品情報 |
| メーカー |
スリーハイ |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
- ●デジタル温度コントローラ・温度調節機器の温度センサ
|
| 検出対象 |
- |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
ガラス被覆:常用温度:250℃(スリーブ 80℃)、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)
シリコン被覆:常用温度:180℃(スリーブ 80℃)、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%) |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
5.0 |
温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)の詳細はこちら
T-35型 シース熱電対(非接地)

耐熱金属管(SUS316)内に熱電対素線を入れ、高純度の絶縁材で充填封止したシース熱電対は細く、応答性に優れており、かつ堅牢に製作されています。シースから絶縁された非接地型でSUS316を採用しているため、ガスなどによる腐食にも強くなっています。
| 商品情報 |
| メーカー |
坂口電熱 |
| 型番 |
|
| 使用用途 |
|
| 検出対象 |
温度 |
| 検出方式 |
- |
| 検出距離 |
- |
| 出力方式 |
- |
| 保護構造 |
- |
| 使用周囲温度 |
- |
使用温度範囲
(被覆材耐熱温度による) |
~800℃ |
| 耐電圧 |
- |
| 本体重量 |
- |
| レビュー(☆) |
4.2 |
T-35型 シース熱電対(非接地)の詳細はこちら
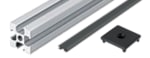
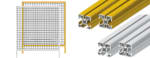




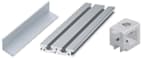

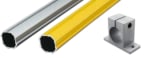
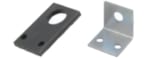
















































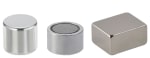




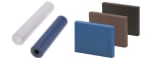

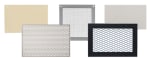



























































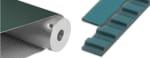



































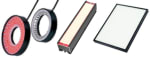
















































































































































































































































































































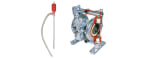































































![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](/pr/kw_select/sensor/img/item_15.png)





![ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/v1/p/jp/product/series/221004951330/221004951330_001_20230801115837.jpg)

![小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/v1/p/jp/product/series/221004951240/CX-411_t_20230801115837.jpg)


