ここまでに数々の近接センサをご紹介してきましたが、これだけの製品のなかから即座に最適なものを選ぶのは、容易ではありません。
そこでここからは、近接センサを選ぶ際に重要となるポイントを紹介します。
検出距離
近接センサの性能でまず重視したいのが、検出距離の長さです。
どの種類の近接センサも、基本的には至近距離でないと対象物を検出できません。
ですが、数mmでも検出距離が長いものを使うことで、多少なりとも余裕をもって機器を設置できます。
ただし、検出の精度を高めたい場合には、検出距離が短い製品のほうが適している場合もあります。
こうしたポイントを検討する際は、カタログスペック上の検出距離だけではなく、実際の環境で使った場合にどう機能するかまで考慮できると理想的です。
対象物のサイズや通過する際のスピード、ベルトコンベアの凹凸など、環境的な要因によって実際の検出距離にはばらつきが生じるためです。
検出距離が適切な近接センサを選ぶためにも、使用環境を事前に明らかにしたうえで、可能であればサンプルを用いて実測を行いましょう。
動作原理
冒頭で説明した通り、動作原理が違えば検出可能な物質も変わります。
そのため、使用用途に合わせて最適な動作原理の近接センサを導入する必要があります。
もっとも一般的な誘導型は、堅牢な作りでありながらも、比較的低価格で手に入るのが強みです。
ただし検出できるのは金属のみであるうえに、周囲に検出対象物以外の金属があると検出距離が不安定になるため、使用用途はある程度限られます。
金属以外にもさまざまな物質を検知する必要があるなら、静電容量型を選ぶのが適当です。
ペットボトルやガラス製品の内側にある物体も検知可能なので、多種多様な用途で活躍してくれるでしょう。
また、対象物が磁性のあるものと決まっている場合は、低価格で導入できる磁気型が最適です。
サイズと形状
動作原理と合わせて、サイズや形状の分類でも近接センサを選別しましょう。
特に誘導型は、検出距離がセンサの直径の半分に比例するので、検出距離を長くしたい場合にはサイズの大きい製品を選ぶのが得策です。
また、先述した通りセンサの形状の違いによって取り付け方法も変わってきます。
環境次第で、取り付けられる形状や対応している取り付け方法は異なるので、この点も入念に検討しましょう。
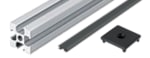
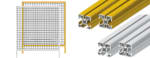




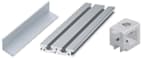

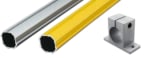
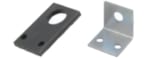
















































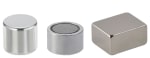




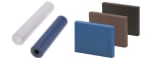

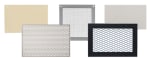



























































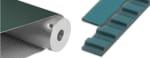



































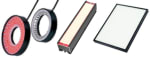
















































































































































































































































































































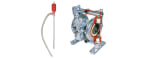























































![角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)](/pr/kw_select/proximity-sensor/img/item_07.png)






![超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/v1/p/jp/product/series/221005013183/221005013183_20230801115837.jpg)


